 |
| since2004― |
|
  |


Pet4You.jpのエコ活動

「GIO」と「ECO」のコラボレーション

ベアドッグの育成でお世話になっています

環境との調和をめざすリゾート
オススメ!
|
 |
 |
 |
2010年代後半あたりから、北海道各地でヒトをそれほど警戒せず、特に大した目的もないのに市街地や住宅地に侵入しフラフラと歩き回るヒグマの事例が散見されるようになった。多くの市街地出没に対して考察をおこなっていくと、「ヒグマの生息数が増えた」「耕作放棄地によってバッファが消失した」「ヒトの生活がヒグマの生息地に食い込んだ」「山の木の実が少ないから」などなど、一般的な専門家が指摘しているようなことは確かにあるのだが、それらは間違っているとまでは言えないものの「主因」と言えるほど大きく強いファクターではない。
というのは、私がヒグマの調査や対策をおこなって来た丸瀬布のような中山間地域では、周囲の山はもともと潤沢なヒグマの生息数を持っていて、バッファスペースなどほとんどなく、ヒグマの生息地からいきなり住宅地・市街地になっていたりする。にもかかわらず、前世紀の80年間、武利の集落にヒグマが侵入したことなど一度もないという。古参の住民によってもあり得ないヒグマの行動が、今世紀に入って立て続けに起きた。それは箱罠を導入し大量捕獲をおこなった数年後のことだった。
もし仮に、裏山のヒグマの生息数とかバッファスペースの有無が昨今のヒグマ出没の主因だとすれば、丸瀬布など慢性的に札幌の何倍も市街地や住宅地をヒグマが歩き回る場所になる。だが、それが起きてこなかった。つまり、昨今のヒグマ問題は指摘されているような単純な論では到底片付けられないわけだが、近年のヒグマの問題群の主因として「ヒグマの無警戒化」が大きく関与していると考えている。
仮にそうだとすると、「どうして最近のヒグマがヒトに無警戒になるか?」という命題があり、そこを解き明かすこと抜きに十分合理的な対策は打てないだろう。「クマはヒトの鏡」からすると、ヒトの暮らしや行動の変化・人間社会の変化がこれらのヒグマの変化をもたらしていることはまず確かだが、ヒト側の幾つかの変化・理由が絡み合い、全体像はそう単純ではなさそうだ。
その「無警戒化のメカニズム」に関しては追々言及するとして、まずは、どのようなアプローチでこの問題に対抗すればいいかを考えてみたい。
北海道の現状と対策
下図は、北海道の2011年上半期の、捕獲されたヒグマの年齢内訳を表すデータ(道庁)のグラフである。赤い棒グラフがこのウェブサイトに再三登場する若グマ(1歳~5歳)で全体の73.5%にのぼる(一部仔熊を含む)。5歳程度までのクマを生物学では身体的にまだ完全な成獣まで成長していないという意味で「亜成獣」とも呼ぶが、まだまだ経験不足で心理的にも成長過程にあるヒグマと捉えられる。
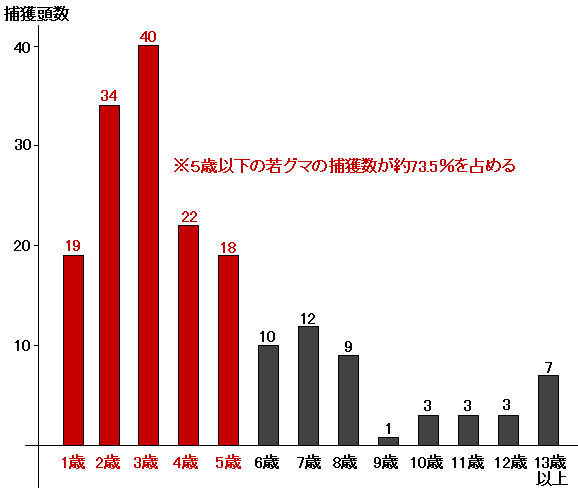
このグラフから、ある一つの仮定でシミュレーションをおこなうことができる。5歳までの若グマに対して教育的な働きかけをおこない、意識改善・行動改善をおこなわすことができれば、ヒグマ問題自体が総じて減少し、捕獲数も下げることができる。その「ヒトを警戒し忌避する」という教育効果が若グマの中で固定化するところまで教育できれば、その個体が将来にわたってその習性で活動することが期待でき、グラフ中の黒い部分(6歳以上の捕獲数)も一定のタイムラグを持ちつつ自動的に減少へ向かうことが予想される。
またさらに、教育達成個体がメスの場合、母系伝承が作用し次世代以降の個体にそのメスの好ましい習性が受け渡されるため、若グマへの教育活動を地道に続けることにより、問題が効果的に解消へ向かいつつ、若グマ教育の活動自体が容易になっていくことが推測できる。
※現在までの北海道においては「捕獲=捕殺」を意味する。
上述の仮定から出発すれば理想的な結果が次々に導かれるわけだが、問題は、その仮定の実現可能性だ。成長過程の若グマに対して、ヒトへの警戒や忌避を植え付け、固定化まで持って行ける教育手法が具体的に存在するか否か。そこが最大の焦点になる。
無警戒タイプの若グマ
前項で述べたように、人里・市街地・商店街・キャンプ場周辺などを明確な目的なしに歩き回ったりするクマには大きく分けて2種類ある。
まず、経験不足で無知な学習途上の若グマ。こちらは、若干の不安を持ちながら旺盛な好奇心でフラフラと行動する若グマタイプで、昔からあちこちにいたタイプだ。単純に無経験で警戒心がまだ乏しいだけの若グマなので、好ましい経験を積ませることで容易に行動改善まで持って行けるが、都市部や観光エリアで柔和で軟弱なヒトに接しているうちに、下述の新世代タイプになってしまう率も高い。
もう一つは、観光エリアや都市部周辺で幼少の頃よりヒトの存在に馴化し「ヒトは無害である」と学習して無警戒になった新世代ベアーズタイプ。母グマが若く警戒心に乏しい場合には、仔熊はこれになりやすい。こちらは、経験と学習によって無警戒になったヒグマで、必ずしも若い個体とは限らないが、よほどヒトから接近するとか追い詰めるとかして切迫させなければ、ヒトに対して消極的で感情があまり動かない。「ヒトは無害・安全」と一度学習し固定化まで進んでいる場合も多く、その意識改善・行動改善は単純タイプよりは難しいことが多いが、年齢が若ければ工夫によって修正は十分可能だ。私の印象では、現実的に教育可能な年齢はオスメスともに4歳程度までか。
両者は「ヒトに対して好奇心を持っているかどうか」で見分けがつくことが多いが、ちょっと見ただけでは判断がつかないケースもあるので厄介だが、特に今世紀に入って増えている新世代タイプについて、どうしてこのタイプが現れ、北海道全域で増えているか。その原因について重要どころを整理しておきたい。
原因1:クマ撃ちの減少
一つは、クマ撃ちの減少もしくは欠落が原因として考えられる。クマ撃ちというのはヒグマをよく知り、銃を肩に山へヒグマを追い仕留めることのできるクマ猟をおこなうハンターである。シカ駆除と称してクルマに銃を積んで林道類を徘徊し、偶然見かけた若いクマをいくら殺しても、それは単にクマを殺した人であって「クマ撃ち」とは呼ばない。そのクマ撃ちが現代では風前の灯火で、「クマが絶滅する前にクマ撃ちが絶滅する」と冗談めいて言われてきたが、実際、専門家の間では大きな懸念となっている。実際私の暮らす丸瀬布においても、もう20年以上クマ撃ち不在が続いており悩みのタネになっている。
北海道各地に存在したクマ撃ちは、クマを追い、あるいは待ち構えて射程に入れクマを獲ることができたが、自然な成り行きで用心深く逃げ切るクマも多くいた。現代の「流し猟」的なシカ駆除とは異なり、いろいろを観察し知恵を絞って臨んでもクマに感づかれて逃げられる。だから狩猟としても価値があった。つまり、クマ撃ちがクマを撃ち殺したからではなく、クマを追って山を歩き回ることで、結果的にクマに対してヒトを警戒する心理を植えつけてきた側面がある。追われて逃げるクマは「自分は逃げる者」「ヒトは追ってくる者」と脳に刻み込んだだろう。そのクマの意識がヒトを警戒させ、結果的にヒトが多数活動する人里や住宅地・商店街から遠ざけたし、北海道でヒグマが簡単に目撃できず、いつまでも得体の知れない山のモンスターであり続けた理由でもあった。
ただ、この理由はクマ猟の副産物として派生的にクマに学習させていただけで、クマ撃ちは単にクマを獲物として追っていたに過ぎずクマを教育しようとしていたわけではない。また、特に誤解をしてはならない点は、クマ撃ちがクマを獲ろうと追いつつ、彼らの望みとは逆に逃げ切るクマが重要だった点だ。追うクマを銃で射殺してしまっては、じつは意味がない。ヒグマの側にヒトへの忌避・警戒心をガッチリ植えつけつつ、逃がすことに意味がある。ヒトを警戒し忌避するようになった個体がメスならば、そのクマは仔熊にそれを伝承し、クマ社会にヒトへの警戒心というのが一種の文化として広がっていくことにもなる。
補足2)ヒグマの社会と文化性
このように表現すると訝しげに思う人もいると思うが、いったんその先入観を取り払って欲しい。
例えば「食」について考えてみよう。道南方面では稲(コメ)がヒグマの被害に遭う。名寄市周辺では、稲・小麦は被害に遭わないが、丸瀬布では小麦はデントコーンに次ぐ被害作物だ。ところが、斜里でさんざんな被害に遭うビートは、丸瀬布ではクマにはまったく見向きもされない。
これは2010年当時のデータで今どうなっているかはわからない。つまり、「食」に関しても、「ヒグマはこれを食べる」とすべて決まっているわけではなく、地域性がある。では、その地域性はどうして生ずるか? それが、母系伝承をはじめとする社会的なメカニズムである、というのが私の解釈である。
丸瀬布においてもビートの農地にクマ用の電気柵を張らず、ハネモノを農地の脇に山積みにしている現状では、あるときどこかのクマがそれを食べ、そのエリア一帯のクマにいろいろな伝わり方をして、そのうち「丸瀬布のクマはビートを食べる」という状況が生まれるだろう。それにかかる時間は、さほど長くない。
伝わり方には先述の母系伝承のほかに、例えば単純なところをいえば、ビートを食べたクマの糞を別のクマが見つければ、嗅覚によって何を食べたかは手に取るようにわかる。そして、糞をしたクマの跡を逆に追ってビート畑を速やかに突き止めることができ、当然食べてみたくなるのがクマ情だ。一度食べてしまえば、ビートならばその後常習的に毎年食べるようになるだろう。この連鎖でその地域のクマのほとんどに「ビート食」が伝わり恒常化し、「その地域のクマの文化としてビート食がある」などと表現しても的を外さなくなるわけだ。
これに似たクマの社会的な伝搬が「無警戒化」にも存在する。trap-shy(トラップシャイ)にも存在する。
※trap-shy:ヒグマがワナを警戒しワナが利かなくなる性質。(参照LINK:箱罠のリスク)
|
原因2:銃器の高性能化
「銃器の高性能化」というのは意外かと思うが、私自身はアラスカでもともとクマからの護身と食糧調達のためにショットガンをほとんど常に携帯していた。友人のアラスカのハンティングガイドとともに猟に出たりもしたが、現代の高性能ライフルとショットガンでは、その射程が5倍程度違う。1頭のシカを撃つにもライフルなら500mの距離から比較的正確にシカのネックを撃ち抜いて即倒させられるが、ショットガンでは100m内外まで接近しないと確実には仕留められない。友人は私にしきりにライフルと勧めたが、私はショットガンにこだわり続けた。私の場合、クマに対しては30mの性悪な相手をいかに確実に倒すかが大事で、遠射の必要性を見出していなかったからだ。
結果的に、遠射技術の代わりに私は野生動物に接近する技術を手に入れた。シカを木陰で待ち構えて脇腹を突いたり、ヒグマ相手のダルマさんが転んだをやったり、恐らく、さしたる望遠レンズを使わずヒグマを写真に撮れるのも、その頃の技術の名残かも知れない。
さて、渡島半島では春期の人材育成捕獲として春先の積雪期にヒグマを銃器で捕獲する取り組みがおこなわれていたが、視界の開けたこの時期にはクマの足跡も追いやすく、遠射が利く。それでその春季捕獲では沢を挟んで400m離れた場所などからたびたびヒグマが射殺された。私の印象では、その銃も弾もそれなりにきっちりチューンナップされたものだったと思うが、こういう精密射撃を可能にした道具仕立てだと、ヒグマはヒトに追われていることにも気づかず突然銃弾を撃ち込まれ即死したりするので、ヒグマに対しての教育効果がほとんど期待できない。
と同時に、ヒト側のクマ撃ちとしての人材育成効果もほとんど得られないだろう。というのは、駆除などを要する非積雪期においては藪や葉が生い茂り、400mも見渡せる場所自体が皆無で、先述した私の距離、つまり30m先のヒグマをいかに確実に仕留められるかが要求されるケースのほうがはるかに多いからだ。
ヒグマへの教育効果・人材育成効果をどちらも効果的に得ようと思えば、春季捕獲のレギュレーションに「使用する銃器は12ゲージのショットガンに限る」という一文を盛り込めばいい。ヒグマに気づかれずショットガンのレンジにまで近づくことができ、冷静さを保って12ゲージを苦もなく使いこなすことができるようになれば、クマ撃ちが用いる338WinMagあたりを楽に扱え、ほとんどドロップやドリフトを計算せずヒグマをあらゆるレンジから仕留めることができるようになるはずだ。
クマ撃ちに最も重要な資質・技術は、銃器の代わりにイヌを連れヒグマを蹴散らかすBDハンドラーと同一で、近距離にヒグマを置いた状態でいかに動ずることなく冷静に判断し動作できるかであって、射撃の遠射能力では決してない。
もちろん、視認できるヒグマに対してスコープを用い高性能ライフルを発砲するのに比べれば、脇の藪に潜んだ見えないヒグマに対して高性能なベアドッグを放つほうが、ヒグマに対する教育効果が高く、スリリングで、面白くもある、と思う。クマ撃ちとBDハンドラーの能力は変わらなくても、殺傷能力以外のすべての点で銃器よりベアドッグに利があるからだ。
なお、過去の春季捕獲で、その捕獲実績とその年のヒトとヒグマの軋轢度の間で相関が見られたことはなかったと記憶するが、効果が全くないとまでは思わないものの、ハンター側がすこぶる有利な条件でアトランダムにヒグマを何頭か殺したところで、被害防止には大して結びつかないだろうということは推して量るべしの範疇だ。
原因3:無分別なヒグマ捕獲―――捕獲リバウンド現象
しかし、道内各地でいっせいに無警戒型が現れるのは、クマ撃ちの減少(または欠落)だけからは説明できない。何か別の変化が人間社会側にあったはずだが、2004~2010年の丸瀬布における観察で浮上してきた原因がある。「無秩序なヒグマ捕獲」というのがそれだ。
北海道でもヒグマの生態はいろいろ研究されてきたが、社会学的なことはこれまでほとんど研究されていない。その結果、ただ単純に「クマは殺せば殺すほど被害が減り安全だ」的な安直な考えが北海道では漫然と続いてきた。しかし、今世紀に入って道内各地に導入された箱罠(はこわな)によってヒグマの捕獲数が跳ね上がるとともに、無警戒型のクマが各地に現れてきた時期的な符合は見逃せない。これは従来的な生態学だけからは説明できない現象である。
私の暮らす丸瀬布においても、一時期、箱罠によってそこそこクマが獲れるようになったにもかかわらず、目撃数や出没が増え、出没パタン・場所も悪い方向に変化してきた。「最近、クマがおかしい」「急激に増えた」とまるで口裏を合わせたかのように行政・ハンター・農家が言い始めたが、ただ不思議がるだけで「どうしてそうなったか?」を矛盾なく説明できる人はいなかった。もちろん、研究者・専門家にも。誰も説明できないのであればいったん箱罠の使用を中止してもよかったが、丸瀬布ではただ惰性で使い続け、一部のハンターは見かけただけのクマを撃ち殺し続けた。私はその行政対応に一定のストレスを与えつつ、この不思議な現象を「捕獲リバウンド」と名付けて箱罠導入年の2004~2023年まで約20年間ほど追って来たが、ようやく事実の詳細や傾向が整理できて「どうして?」に対して理路整然と確信を持って答えられるようになった。(参照Link:ヒグマのアドバンス/捕獲リバウンド)
捕獲リバウンド現象は、ヒグマが不在の空間に再びヒグマの活動が戻ってくるときのシンドローム(症候群)で、様々な現象の総体だが、その中に「ヒグマの無警戒化を促すファクター」が隠れている。
従来的にはいわば小学生の算数のような計算でヒグマ対策がおこなわれてきた。つまり、10頭いるクマのうち1頭殺せば10-1=9と9頭に減るため被害が減り安全になると。しかし実際はそんなに単純なものではなく、1頭減ったことによるヒグマ社会のバランスの崩れや、その崩れたバランスを回復させるためのメカニズムがある。その1頭が活動していた空間がヒグマ不在の空間となり、その空間がその後どう変化するかまで読んで1頭の捕獲判断をしないと、まったく予期せぬ事態が起きてくる。丸瀬布に見られる「クマをどんどん獲ったらクマが急激に増えた。最近クマがおかしい」と少なくとも行政やハンター・農家には見える状況が生まれたのは、まさにそれだ。目の前の場当たり的な一頭より、むしろそれが欠落したあとの長い目で見たトータルな判断のほうが、はるかに重要なのだ。
丸瀬布では箱罠導入年の2004年に狭いエリアで10頭ほどの大量捕獲があり、捕獲リバウンドがあちこちで起きたため顕著にいろいろな変化が感知できたが、近年、北海道各地のクマの問題傾向やパタンを見ていると、多くの市町村・地域で大なり小なり同様の現象が起きていると推察できる。小規模な捕獲リバウンドは、あちこちの地域で起きているのではないかと考えられる。
原因4:柔和で無害な現代人特性
「新世代ベアーズ」とはじめに表現したのは知床の山中正実さんだったと記憶しているが、知床型の無警戒タイプは、その後、大雪山の高原沼周辺にも現れ、2006年前後から丸瀬布「いこいの森」周辺の観光エリアにも明らかな予兆として現れた。丸瀬布の観光エリアにおいては予兆の段階で即座に追い払いなどをおこない、次いでベアドッグを導入して若グマの忌避教育を体系的におこなってきたためエリアのヒグマの無警戒化を一定レベルで食い止めることができたが、道内幾つかの観光立地の地域でも無警戒タイプの若グマがちょくちょく見られるようになってきた。
当初、ヒグマの生息地内もしくは隣接する観光エリアに特有の無警戒グマかと思われたが、札幌西区・南区で地下鉄の駅の周辺にまで歩き回るクマが出たり、旭川のベッドタウンとして発展しつつある東神楽の住宅地周辺でも過去にないヒグマ出没が起き始めた。札幌・東神楽に関しては偶然調査をおこなう機会に恵まれたため現場のいろいろを見て回ることができたが、観光地における新世代ベアーズと大都市周辺の無警戒タイプができあがるメカニズムが同一であることがわかってきた。
知床の岩尾別・丸瀬布「いこいの森」・大雪山の高原沼であれば、膨大な数の観光客の活動に隣接して暮らすクマが徐々に「ヒトは無害である」と学習し、最終的には人目を気にせず無頓着にマイペースで活動するクマができあがるし、札幌・旭川などの大都市周辺部では、住宅地などがヒグマの生息地に食い込む形で発展し、やはりその周辺の山のクマがそこに暮らすヒト・活動するヒトを無害であると学んで無警戒化が進む。無警戒な若グマが母グマとなり、その環境で子育てをおこなうと、その仔熊はさらに無警戒な若グマとして親離れし、ヒトとの間に軽率なトラブルを起こしがちだということも「いこいの森」周辺の対策エリアで徐々に確かめられた(2009~2012)。
つまり、アウトドアの観光エリアと都市部およびその周辺において、ヒトに対する無警戒化が進んだ新世代ベアーズが発生する共通の条件が潤沢にあることが示唆されるが、それが特に「現代の都市生活者特性」と考えるとつじつまが合い、さらにその根本は何かというと「現代人の自己家畜化」という文化人類学的な領域の事象が浮き出てくる。
知床にせよ丸瀬布にせよアウトドア観光における観光客というのは 都市生活者の比率が圧倒的に多く、その感覚・行動パタンを無造作にヒグマの生息地に持ち込んでいるとも捉えられる。その現代の都市生活者が集まって生活するのが都市部だとすれば、当然その周辺では、観光地に持ち込まれる感覚や行動が溢れていることになり、それに接し続けるヒグマは同じ影響を同じメカニズムで受けて変化する。それが無警戒化だ。
現代人の自己家畜化とは、現代人が現代社会に最適化しつつがなく暮らせるように自らの感覚やライフスタイルなどを変化させて適応することを意味するが、その最適化や適応というのは現代の人間社会の内部だけで通用するもので、同じ人類でも江戸時代の日本にも適応できなければ、自然界・野生動物に対してはもっと適応力を持たない。感覚的なカルチャーギャップなわけだが、要するに、動物としての基本的な能力が現代人においてはかなりスポイルされている面があって、特に高知能な動物との言語を介さないコミュニケーション能力に欠け、やりとりをおこなって両者の活動範囲や優位性などでバランスをとることがほとんどできない。にもかかわらず、相手を殺して排除する銃器という文明の利器だけは持っているので、捕獲一本槍が延々続いてみたり、殺して数を調整するなどという方法論に頼ったりもする。目障りな動物の個体数調整などをおこなう動物はいないし、それがなくても十分持続的にバランスはとれるよう自然界はできているのだけれど。
近年の都市部や観光エリア周辺で起きるようになったヒグマの出没の主因は「ヒグマの無警戒化」と話し、その無警戒化のメカニズムに「都市生活者の特性」「現代人の自己家畜化」が深く関わっていると説明してきたが、この部分はとても重要なため、補完文章としてpdfをリンクし添えようと思う。
「現代人の自己家畜化について」(pdf)
丸瀬布においてクマに働くいろいろが非常に見えやすかったのは、2004年以降、上の三つの原因すべてが綺麗に揃っていたからである。つまり、クマ撃ちが不在で、漫然と箱罠を多用し捕獲一本槍に走り、なおかつ「いこいの森」を中心とした一大アウトドア観光エリアが町の立地条件になっていた。
この難解なエリアでどうやってヒグマの無警戒化を食い止め、捕獲リバウンドで起きた「若グマのるつぼ」的な混沌としたクマの社会構造をもともとの安定したクマ社会に戻してきたかは、別項を参照して欲しい。その方法論の最も合理的で効果的な具象化としてベアドッグがある。
補足1)ヒグマの無警戒化の検証と対策のヒント(at丸瀬布)
私が調査・対策エリアに設定した中央部には、遠軽町が運営するアウトドアレジャー施設「いこいの森」と、リゾートホテル「マウレ山荘」があって、そのほかに武利ダム・武利川をはじめとする釣り人来訪や、各種アウトドアレジャーで年間の集客力は20万人程度と推計されている。中でも「いこいの森」はここ30年設備を増やし続け、キャンプ場・昆虫館・パークゴルフ場などを備えた一大多目的アウトドアレジャー基地に成長したが、ゴールデンウィークから10月までの約半年間の開園期間で集客力15万人を誇っている。
開園期間中、いこいの森には、のべつ幕なしにキャンパーが訪れ、クルマが行き交い、園内の林業機関車が汽笛を派手に鳴らす。夜になると、訪れたそれぞれがバーベキュー大会や花火をおこない、夏休みには盛大に観光祭りや花火大会がおこなわれる。訪れる人は観光気分でやってくるので、ちょっとした都会より、はるかに派手で騒がしいヒトの活動がここにはある。
周囲の山はヒグマの大生息地で「北大雪(きたたいせつ)」とも呼ばれるが、その山塊全体でヒグマの生息数は、正確ではないものの500絡みではないかと推定している。とにかく潤沢なヒグマの生息数がある。
では、その膨大な数のヒグマは、この騒がしいアウトドアレジャー基地を避けて暮らしているかというと、それは否。正確に言うと、警戒心を持ったオス成獣は総じてこのエリアを避けて暮らし、そのオスを避けるようにメス熊や若い個体は、むしろのこのレジャー基地に寄り添うように活動する傾向が強い。
2004年の箱罠導入年以降、このエリアでは「捕獲リバウンド現象」の影響で「若グマのるつぼ」状態と化したが、そのるつぼの中を調査で歩いていると、ときどき異様な感覚に襲われることがあった。例えばある親子グマの追跡をおこなっていて、ふと斜面の下を見ると、すぐ下に「いこいの森」の喧噪があったりした。親子グマの追跡地点から、キャンパーの顔の識別ができるほど近い距離。
つまり、「いこいの森」の裏斜面育っている仔熊は、生まれたときからヒトの喧噪やクルマの排気音や花火やバーベキューを、すぐ身近に感じながら育っていることになる。恐らく、その仔熊は多くの人が近くに居て当然と認識していて、このクマに対して「ヒトを警戒せよ」とただ要求しても到底無理なのだ。そういう事情が働いて、「いこいの森」周辺でヒグマの無警戒化が非常に起こりやすくなっている。
似たような現象は、同じくヒグマの生息地に囲まれた観光エリアでもあるだろうし、都市部周辺のボーダー付近でも起き得る。
2009年、親離れしたての若グマで非常に警戒心の薄い個体が感知された。そのクマをマークし、追跡や現認をおこなったが、行動パタンからメスと推定し、通常ならすぐさま追い払いをおこなうなどして行動改善を促すところだったが、あえて放置しその個体の経過を観察した。
当初、私が予測したのは、そのメス熊が子を持ち、その仔熊が親離れして独り立ちした後に、ものメスが輩出した若グマのどれか(もしくはすべて)が何かをやらかすだろうということだった。キャンプ場や集落にフラフラ入ってくるとか、遭遇したヒトの前で暢気に振る舞うとか、そんなことだ。
推測通りその個体はメスで2011年に2頭の子を連れて歩くようになったが、相変わらず無警戒のままで、日中の町道を仔熊ともども暢気に歩いた。監視体制を強めてさらにその親子を放置し観察した。そして2012年、7月中旬頃2頭の仔熊は親離れを果たしたようだが、8月に入りそのうち1頭が上武利集落の日中の徘徊をおこない大騒動となった。年輩の住民への聞き取り調査では、「過去のこのようなヒグマの出没は一度もない」とのことだった。やはり放置すれば「いこいの森」を中心にヒグマの無警戒化が進む。そう確信した騒動でもあった。
この日中徘徊をやらかした若グマに対しては、即座にベアドッグを用いて追跡をし一定の威圧をかけてその後の出没を消し、問題のメス熊と同胎に対しても同様の威圧をかけつつ数度の追い払いをおこなってヒトへの警戒心を引き上げた。その結果、その後この3頭が許容できない行動を「いこいの森」および上武利集落付近でとることはなくなった。
このメスは、2023年現在、まだ「いこいの森」裏の斜面を活動の場とし、順調に仔熊を産んで育て上げてくるが、以前ほど「いこいの森」に接近することはなく、また、問題を起こすような若グマを輩出することは皆無となっている。
|
さて、クマ撃ちが結果的に周辺のヒグマに対しておこなってきたことは、ヒグマを撃ち殺すという目的の過程で派生したヒトへの警戒心の植え付け効果だが、これが人間社会にとって好ましい「ヒグマへの教育」になっていた。その教育効果が薄れ十分機能しなくなった現在、再びクマ撃ちを養成して云々というのもなくはないが、意図的にヒグマの教育を狙った専門的な人材の育成のほうが、はるかに合理的だ。その方向では、クマ猟で副産物として得られた教育効果よりはるかに正確かつ大きな効果を安定的にもたらしてくれる。
捕獲・捕殺の専門家としてのクマ撃ちは、それはそれで必要なため育成に異論はないが、ヒグマの無警戒化の阻止に対しては、ヒグマの教育に特化した専門家を養成し、その作業にあたらせるのが最も合理的なスタンスと考えられる。
一方、ヒグマの社会を無視した漫然とした無秩序なクマ捕獲がもたらしたことは、それなりに安定して人里周りに存在していたヒグマ社会を不用意に破壊した結果起きているため、再びもとのヒグマ社会に戻してやる努力が必要となるが、もとに戻るまでの間、ヒグマの無警戒化の阻止としての教育要素を欠くことはできない。
問題は、捕殺と教育、二つの対策が非常に高度な知識・経験・技術を必要とし、危険度も高いため、行政や一般のハンター・住民に担ってもらうのがほぼ不可能という点だ。例えば夜間対応ひとつとっても、十分な想定と準備をし訓練を積んでいなければ正確に遂行できない現実がある。暗い中で一頭のヒグマを藪から追い出したり、誘導したり、山へ追い払ったりという作業は、ことのほか難易度の高い作業なのだ。
かといって、市町村に2~3人のヒグマ専門家がついて、というのも現実的ではない。追い払いまでをきっちりできるヒグマの専門家というのが、じつは非常に少なく、全道でも両手の指で数えられるほどしかいない。
容易にそういうヒグマの専門家を招聘できないとすれば、どんな方法があるだろう。
家庭医的なヒグマ専門家を持つ
ひとつの方法は、一定期間しかるべき専門家に調査に入ってもらい、その地域のヒトの暮らしとクマの状況を調べ、その地域に合った現実的な方法をアドバイスしてもらう方向性があるだろう。もちろんそれでは理想的なヒグマのコントロールや教育はできないだろうが、トラブルが発生した場合、できるだけ早い段階でその専門家に相談し、再び現地を観察してもらって合理的な対策を練る。場合によっては、専門家がしばらくその地に張り付いて問題グマ対応をおこなうこともあるだろう。
ヒグマ対策というのは、もちろん一般論や定型も大事だろうが、地域地域の現状をふまえた臨機応変な対策を必要とする。その点、依頼を受けた専門家はその市町村の家庭医的な立場になる。餅は餅屋というが、素人判断であれこれ悩むより、はるかに無駄なくいい結果を出せるのではないかと思う。
フォーラム・研修会の開催
行政だけでなく住民にクマのいろいろを知ってもらうために研修会・フォーラムを開くのもいい方法だと思う。住民の安全性・被害防止に効果があるとともに、その地域のヒトの意識の変化・暮らしの変化が、周辺のクマの暮らしや性質を変え、問題が緩和する効果も十分期待できる。ただ、お決まりの行儀のいいフォーラムは意味がないとまでは言えないが、あまり効果的とは思えない。単に専門家や研究者が一方的な情報を提供するのではなく、現場の住民・農家・行政・ハンターらと双方向の場となるよう、工夫するのが望ましい。
猟友会とヒグマ専門家の広域連携
その地域の猟友会に確たるクマ撃ちが存在している場合には、調査に入った専門家とクマ撃ちが情報交換を密にとって連携する方法がある。私にもそういう関係の猟友会支部・市町村がいくらかあって、ヒグマを知るという点でお互いに有益でありつつ、銃が使えないケースでは私はベアドッグを連れて飛んで行くし、将来的には捕獲判断をしたヒグマに対して確実な捕獲のために来てもらうこともあり得る。
行政や住民・一般のハンターに難しく、クマ撃ちもヒグマの専門家も数が乏しい状況なら、当然、クマ撃ちと専門家の広域連携が必要で、例えば、クマ撃ちも専門家もいない地域のクマ問題に対して、別地域からクマ撃ちと専門家のチームが駆けつける、ということもあっていい。いや、あるべきだろう。そうなると、その元締めは道庁・振興局という事になるが、総じてゆっくりな道庁の動きを待っていては状況は悪くなる一方なので、自発的にそういう広域的な連携を模索したほうが地域のためにはいい場合もあるだろう。
幾つか例を挙げておく。いずれの場合も対策を練る段階で一度はヒグマの専門家に入ってもらい、ヒグマの調査に加えて、周辺の環境・ヒトの活動(動線)を見てもらうのが先決と思われる。誤解してはならないが、この段階で相談すべきは電気柵の専門家ではなくヒグマの専門家だ。
例1)これまでヒグマなど出没したことのない市街地・商店街などをヒグマが歩き回った。
具体策例)この場合、まず再発防止のために電気柵をメインに用いてヒグマの出没ルートを遮断することを考えるが、そのためにヒグマの侵入ルート(バッドコリドー)の詳細を調査しなくてはならない。その調査結果によって、バッファスペースだけでヒグマの侵入が防止できるケースもあれば、電気柵まで用いないと止まらないケースもある。
ただ、これはあくまで対症療法であって、電気柵やバッファスペースではそのクマにヒトへの警戒心を植えつけないため、その無警戒タイプが市街地などに入ってこなくても周辺の山林で活動する状況は変わらず、釣り・山菜採り・イヌの散歩・ジョギング・トレイルランなどでその無警戒な個体に遭遇するリスクは残ったままだ。
もし仮にそのヒグマをきっちり追跡し効果的な「追い払い」までできる専門家が確保できれば、それをおこない出没したヒグマの無警戒自体を消してヒトやヒトの活動する市街地などへの接近をなくしてしまうのがベストだが、その方法が叶わないとき、そのヒグマに関する情報開示と注意喚起を充分おこないながら、ベアスプレーの貸し出しをおこなうというのもひとつの方法だろう。このタイプのクマのベアスプレーの撃退確率は非常に高いことが丸瀬布において実証されており、スプレーの使い方さえ間違わなければ、まず事故につながる可能性は低い。かつ、もしそのスプレーが使われる事例が起きた場合、その撃退でそのヒグマのヒトへの警戒心が発現する可能性が高い。
注意点は、ヒグマの移動ルートの遮断あるいはルートの移動では、必ず専門家の調査と判断をもとに計画を立て、進めることだろう。その専門家は現場での経験値が高いことが必要だ。不用意に電気柵を設置すると、それが一種の誘導フェンスとなって思わぬ場所にヒグマを誘導してしまう可能性がある。バッファスペースに関しても同様だ。この繊細さがあるため、調査には最低でも1年を要する。
また、問題の無警戒型が生じたメカニズムを現地に照らし合わせて分析し、原因をなくさないと遅かれ早かれまた同じタイプのヒグマが出現し同じ行動をとることが起きるだろう。
例2)農地に毎年出没するクマが、小学校の裏を通る
具体策例)まず、小学校ならびに小学生の通学路が近くにあるような場所では、箱罠の利用は避けたほうがいい。ヒグマの目的地である農地にクマ用の電気柵を回してしまえば問題は一挙に解決するが、それが不可能な場合、ヒグマの農地へのルートコントロールをおこない、小学校近くを迂回するように誘導する。それには上述同様、電気柵とバッファスペースを巧妙に用いる。クマに対して無防備な農地にクマが降りるのは、言ってしまえばクマ側に異常性も無警戒もないし、追い払ってもほとぼりが冷める頃、また農地に侵入してくるため、追い払いは必ずしもおこなわないでいい。
注意すべき点は、クマが出没するからと周辺のエリアを無闇に立ち入り禁止にしないことだろう。気持としてはわかるのだが、ヒトの活動がなくなれば、さらにクマにとっては快適な移動空間・活動空間としてその場所を明け渡すことになるため、結果的にクマの出没は増え、周辺の山に多数のヒグマが生息している場合は、ますますその区域を複数のヒグマが利用するようになる可能性のほうが高い。
この手のパタンは丸瀬布はもちろん道内あちこちに見られるが、原則的に、その場所が人里内ならば、その空間をクマに明け渡すのはいい方法ではない。立ち入り禁止や閉鎖対応をとるのであれば、それ以上にクマを遠ざける要素をその空間に投入しなければならない。人里空間の明け渡しは、よほどの根拠がある場合に限ると思う。
|
|
|
| + |
| Copyright (C) 2014 higumajuku. All Rights Reserved. |
 |
| site map プライバシーポリシー 特定商取引法に基づく通信販売業者の表示――― powerd by higumajuku |







